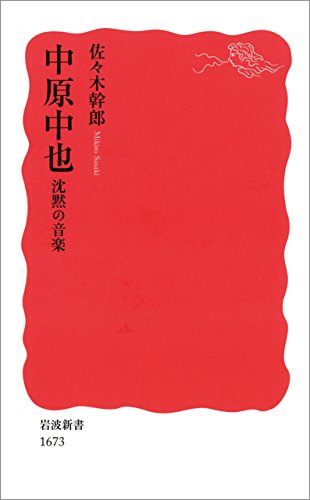エルンスト=カッシーラーの『カントの生涯と学説』(1918年初版)は500ページ近くの大作であり、カッシーラーの代表的な著作の一つに数えられる。

美の判定の分析のための準備
第六章はカントの『判断力批判』を扱っている。
導入的な第一節ののち、第二節ではカントに至るまでの西洋美学史を新プラトン主義の観点から概観する。主なキーワードは、内的形式*1と直覚的悟性(神的知性)*2である。
プロティヌスを源流とする新プラトン主義において、美の理念は有機体(自然や生命現象)へも類推適用される。美と有機体(自然や生命現象)の問題は、カントにおいては「合目的性」というキーワードのもとに判断力の批判の体系に組み入れられることとなる。
さて、第三節のテーマは、合目的性である。合目的性という語の当時の使用状況やコンテクストが、ライプニッツとの関連のうちに明瞭に解読される。*3
そのうえで、合目的性という(あくまで)人間理性にとって(のみ)極めて有用な概念が、多様性に満ちあふれた(ほとんどカオスな)この世界の把握に資するものであるというカントの構想が改めて示される。私たちが生きているこの世界の無限の多様性を(とりあえず)納得的に理解するためには合目的性という概念の助けを借りるしかないとでも言えるだろうか。ここには、世界というものを、ある程度の調和感や統一感、何かしら秩序だったもののうちに見て取ろうとする暗黙の了解が横たわっているようにも思う。カントに言わせればそれこそが理性の性ということになるのだろうか。
合目的性という考え方は、あくまで考察法の一つに過ぎず、客観の定義や主観の認識には何ら寄与しない。にもかかわらず、人間理性にとっては非常に有用な概念である。
ここでの議論をカッシーラーは「問が答えられていないからといって、問が回答不可能とされてはならない」と印象的に総括する。
合目的性という概念に突き動かされる人間理性は、その都度、調和的な世界(世界についての調和的な把握)を希求してやまない。
◆ ◆ ◆
カントの理性批判の議論は、当初、美の判定の客観性を完全否定していた。
美しいかそうでないかは、主観が経験則に基づいてとらえるものでしかない。スープの味が濃いか薄いか、美味しいかそうでないかは、議論しても仕方がない。バラの花が美しいかそうでないかも、同じことである。趣味 Taste の問題は、各個人の、経験の集積でしかない。
かつて『純粋理性批判』の第一版で趣味の原理原則を真っ向否定していたカントは、図らずも、合目的性という人間理性に特殊のアイデアを再考し、それを吟味洗練することによって、美の判定に一定の要件が認められるはずだとの結論に至った、とカッシーラーは述べる。認識論や感性論といった、いわゆる芸術の個別研究ではない領域において、カントの美の判定の理論は誕生したという意外な事実を再確認した上で、いよいよ第四節で本論となる。
美の判定の分析の要旨
カントは『判断力批判』第一部第一篇第一章 美しいものの分析論において、美の判定における四つの要件を提示する。*4*5
カッシーラーの読みはシンプルである。それは、第一の要件こそが全四要件の基礎をなすという洞察である。
感官を感覚において刺激し感官を満足させるものを、我々が「快適」と名づけるならば、また当為の規則に基づいて、従って理性を介して、たんなる概念によって満足させるものを、「善」と名づけるならば、我々は「たんなる考察」において満足させるものを、「美」と呼ぶ。この「たんなる考察」という表現の内には、美学的把握一般の特性をなすすべてのものが間接的に含まれており、美学的判断が出会うそれ以上の規定はすべてそこから導出されうるのである。
単に五感を喜ばせるだけの快楽には埋没せず、かといって、自然科学や数理論理、道徳倫理の領域には決して含まれない、その何かと出会ったときの主観の単なる考察の範囲内における満足が「美」と称されうる。
◆ ◆ ◆
美そのものに目的や概念が想定されるのであれば、すなわち「美」を定義することができるのであれば、それはもはや自然科学や数理論理、道徳倫理の領域である。解析の対象である。
一方で、美の判定は、単なる五感の満足とは異なり、いわゆる一個人のセンスといったものには矮小化され得ない。というのも、たとえば、澄みきった秋の夕焼けを見たときの次のような言明、すなわち「この夕日は個人的にはきれいだと思います。」という言明がはらむ著しい違和感からすると、美の判定は、ある種の公的性質をともなった、無私の満足感に思われてならないのである。
美の判定に関する諸々の議論(いわゆる趣味の問題)は、結局のところ、この第一要件の規定に収束する。
目的や概念、解析の領域ではないが、一定の公的性質を備えた無私の満足感という人間主観の認識の構成(つくり、フォーム、形式)を想定できる領域を、実際のところ、認めざるを得ず、したがってそこには普遍性や必然性への道がおのずと開けてくる、と考えざるを得ない。カッシーラーはおそらくはそのことを端的に述べているのではないかと思われる。
カッシーラーの思索は、いよいよ核心部分に到達する。
ただ美学的機能だけが、客観が何でありどう働くか、をではなく、私が私の内で客観の表象から何を作り出すか、を問う。現実的なものはその実在的性質の方へと後退し、その位置に純粋な「形像」の観念的規定性と観念的統一性とが現れるのである。この意味で、それもこの意味でのみ、美学的世界は仮象の世界である。仮象という概念は、理論的自然概念あるいは実践的理性概念の活動性へと我々を再び引きもどしかねないような、そうした現実性の誤った概念を防ぐことだけを意図するものである。
ここでの仮象という表現にネガティブな意味合いは、まったくない。
仮象 Schein というドイツ語はもともと (1)証明書 (2)紙幣 (3)外見、見かけ (4)光、輝き といった意味を有している。
カッシーラーは、美の判定という特殊領域の確保のため、肯定的な意味でこの語を用いているように思われる。
美学的表象が事象の現存を捨象していること、これこそまさに、美学的表象に備わる特徴的かつ固有の事象性である。なぜなら、ここでこそ、美学的表象は、「諸物」に不可避的に付着する付随的な条件や帰結を、すべて考察外におきながら、純粋形式の直観となるからである。
澄みきった秋の夕焼け空について、それを光学的に解明することもできるし、空と夕日の位置関係や大小関係、軌道を解析することもできる。
それでもなお、夕焼けの美そのものは人間主観に突きつけられたままである。
カッシーラーの思索は、20世紀の現象学を先取りしている。
私の見る色、私の聴く音が、認識する諸々の主観の共有財産として呈示されるのは、両者が外延量・内包量の原則や実体・因果性のカテゴリーの適用によって、精確に認識されうる計量可能な振動へと変形されるからである。しかしこうした量・数の領域への変換によって(・・・)色や音そのものはなくならざるをえない。
色や音を解析すればするほど、色や音は消失していく。
色も音も、数学的には単なる波長である。そして、数学的に解析された波(数式)は、色でもなく、音でもない。究極的な数理解析の結果、世界には、色も音も存在しないという知見が得られる。
数式は、現象の数学的表現でしかあり得ず、現象そのものではない。だとすれば、そのもの自身へと通ずる道は存在するのか。
美学的把握において現象は、その条件に解消されるのではなく、現象が自らを直接呈示するがままに保持される。
美の判定において、条件や目的、前後関係は、留保されている。
それは、第一要件で見たとおりである。
美学的意識はそれ自身のうちに次のような具体的充実の形式を有している。すなわち、その形式によって美学的意識はそのつどの状態性に身を委ねながら、瞬間的状態自身の中で、全く脱時間的な意義の契機を捉えるのである。
ハイデガーへの影響は、疑い得ない。
それにもまして、カッシーラーのカント観は、極めて新プラトン主義的である。
美の判定における時間性の没却という見方は、あきらかに中世思想の影響を受けており、中世思想を理論的に支えたのは新プラトン主義であった。
カッシーラーは、西洋哲学史や西洋美学史のうちにカントを読み解きつつ、現代的な意義を見出す。彼自身はハイデガーやメルロ=ポンティといった詩的言語体系に基づく現象学の道へは進まなかったが、その後の現象学の隆盛や新即物主義への影響ははかり知れない。
1918年初版の『カントの生涯と学説』は、まことに現代の古典である。